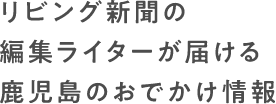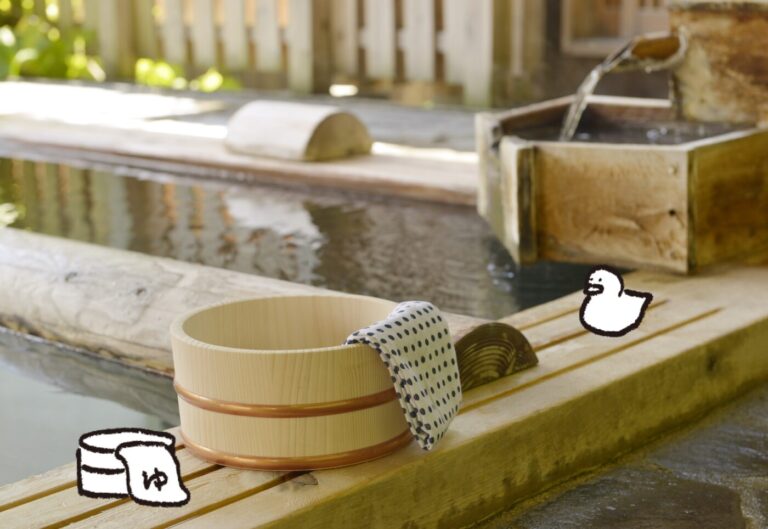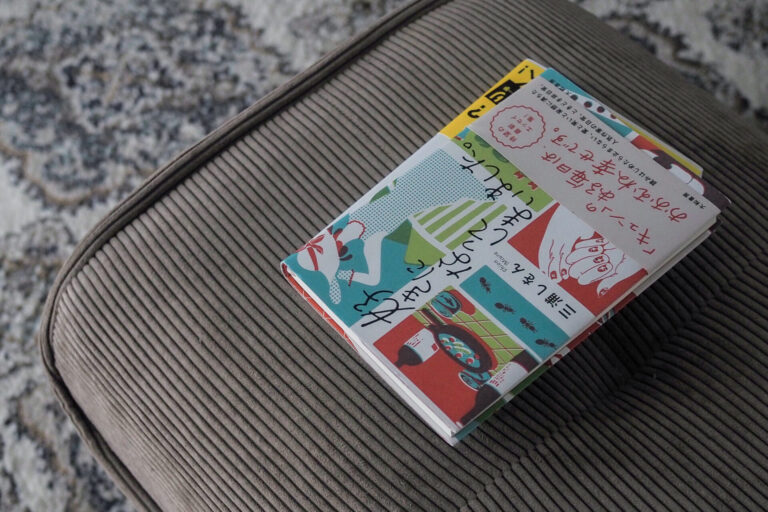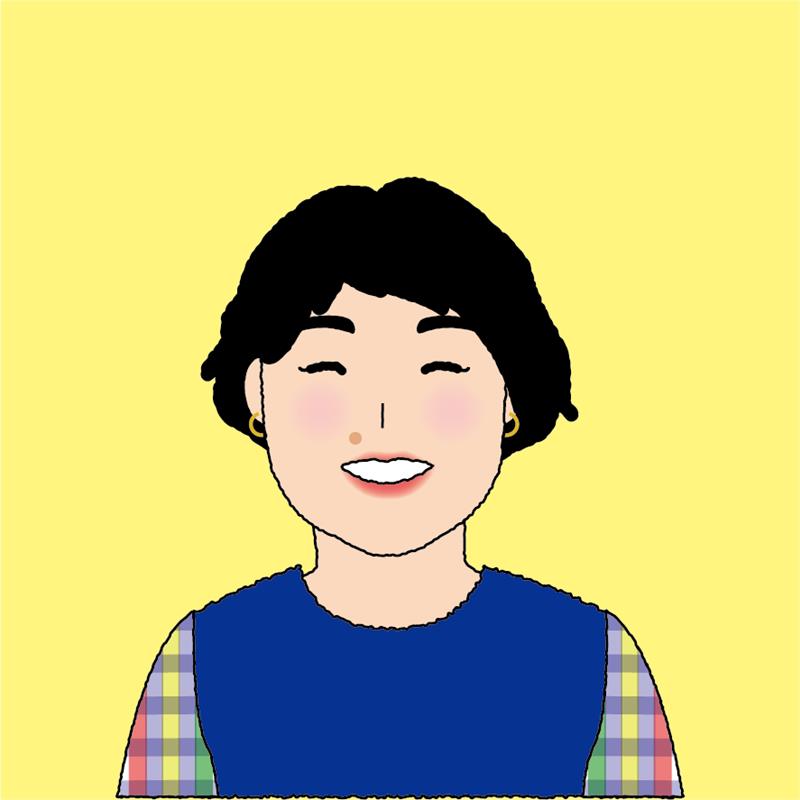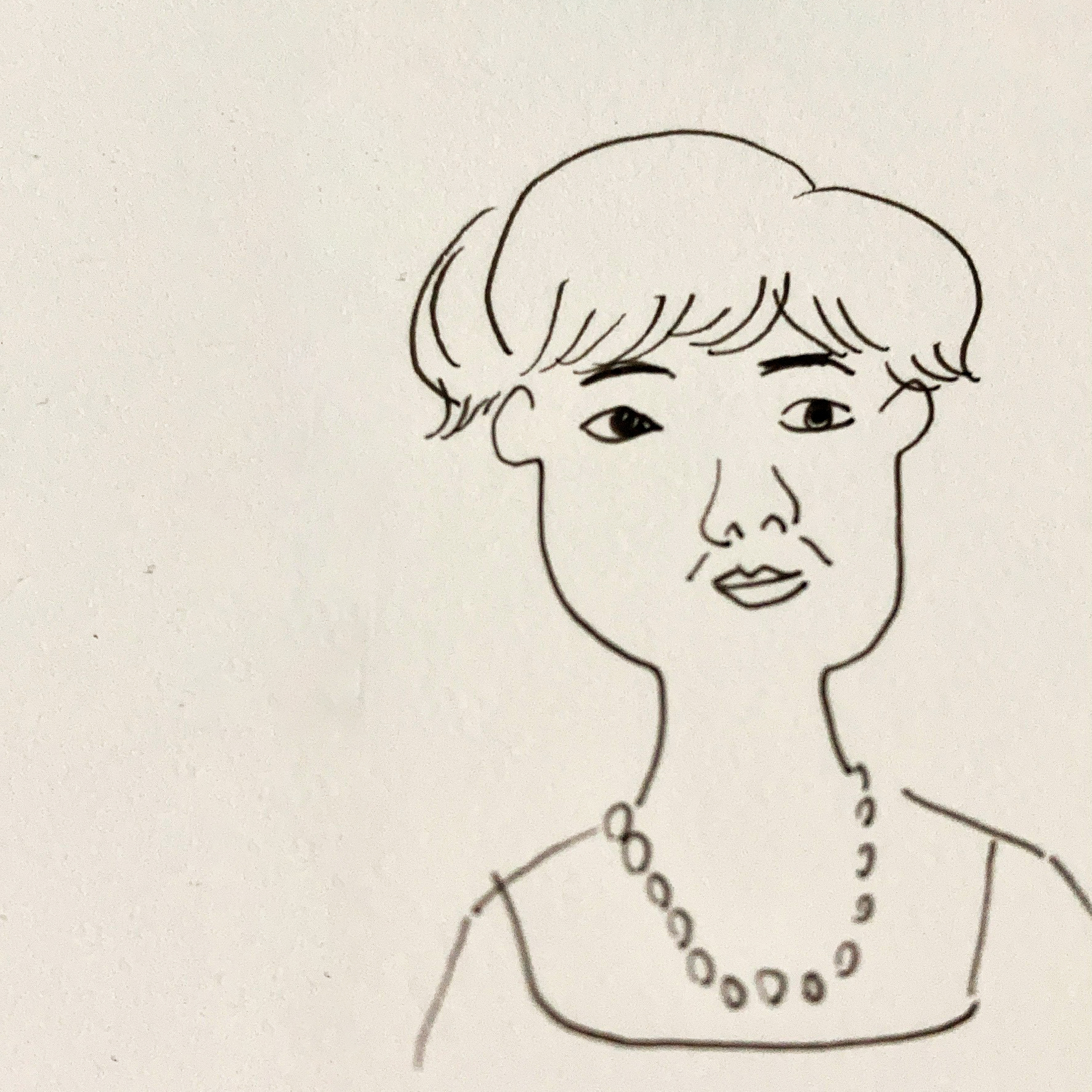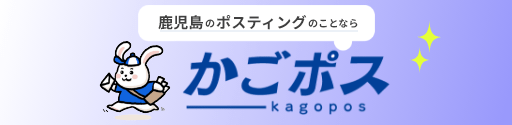1945年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。
毎年8月になると、あらためて「戦争とは何か」「平和とは何か」を考えさせられます。今回は、そうした思いをもとに、私個人の考えを綴ってみました。
10代の頃は、戦争を忘れることを、悪いことだとは思わなかった。むしろ、戦争を知らずに生きられるということは、平和が続いている証だと考えていたから。そんな恐ろしい出来事は、思い出すこと自体が苦しく、むしろ忘れたほうがいいのではないかとすら思っていた。それでも8月になると、学校の授業やニュースで大きく取り上げられる。戦争体験者が少なくなっていくことで、戦争の記憶が風化し、戦争の悲惨さや教訓が忘れ去られていくことが問題視されていた。
今の仕事をしていて「知覧特攻平和会館」の企画展などを見て思う。
空襲の音を知らずにすむこと。
大切なものを守るために銃を持たずにすむこと。
何げない毎日を、当たり前のように送れること。
なんて尊いことなんだろうと。
資料を読み、映像を観るたびに、「どうして、こんなことが起こるのか」と言葉にならない思いが込み上げてきたし、人は同調圧力や恐怖に支配されれば、誰でも愚かな選択をしてしまうのかもしれないとも思った。
争いは、ある日突然始まるものではないのかもしれないし、気づかないうちに、じわじわと始まっていたのかもしれない。
「自分たちのほうが正しい」と信じて疑わなかった人たちは、その正しさを武器に変え、「みんながそうしている」「そうしなければいけない」という空気が、疑問を封じ、分別を奪っていった。声をあげれば抑圧され、非国民だといわれる。そうして歴史のなかで、戦争はさも当たり前のように起こり、人の心を封じたのだ。
以前どこかで読んだ言葉をふと思い出す。
「愚者がみずから愚であると考えれば、すなわち賢者である」
私は、完璧からはほど遠い。まちがいもするし、ときに自分の感情に流されこともある。そう私は愚者。だからこそ、自分もまちがいを起こすのだと認めて、日々や過去、他人から学ぶ必要があるのだと、この年になってようやく気づいた。
社会への不安を漠然ともちながらも、私の平凡な日常の中には戦争はまだ見えない。 でも、それがずっと続いていくように願うなら、私は伝えていかなければならない。
戦争を体験してはいないけれど、その悲惨さを。
そんな思いが、今こうしてこの文章を書くきっかけになった。
次の誰かの「忘れない」につながることを、私は信じている。
これからの平和を願いながら。