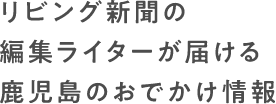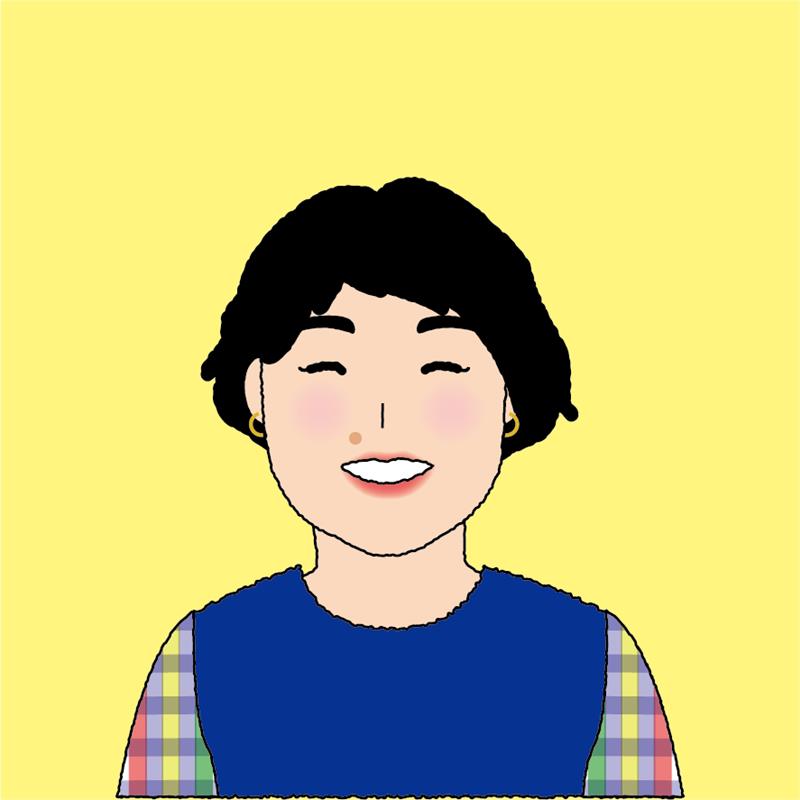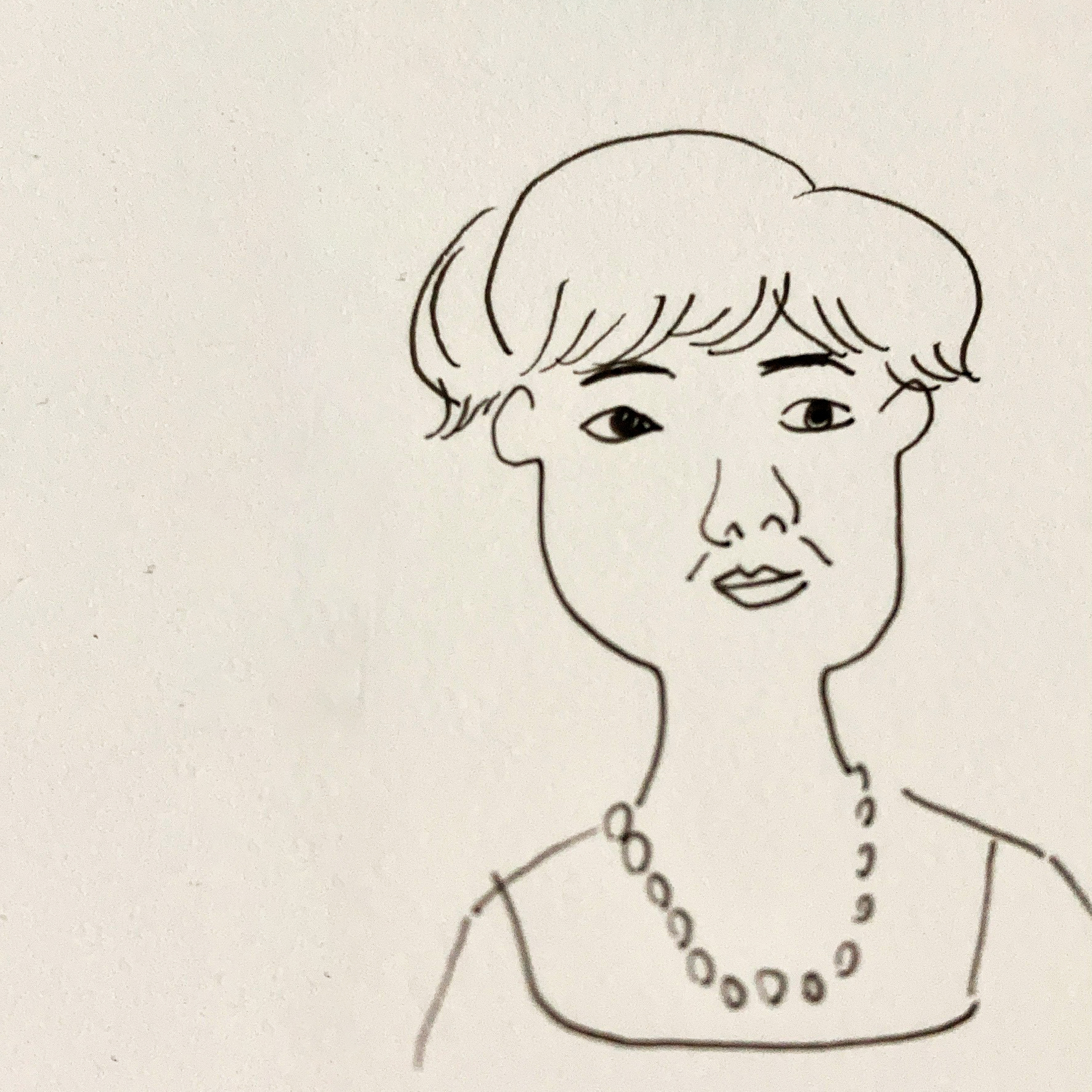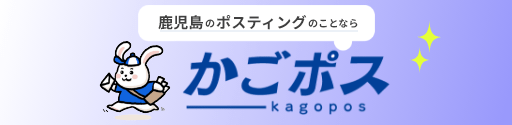山歩きのガイド本で「初級」に分類されている低山でも、登山の難易度はさまざま。散歩道のように歩きやすい「入門レベル」の山から、アップダウンを繰り返す「プレ中級レベル」までありますよね。
秋も深まろうかという10月下旬。久々の山歩きに選んだのは「矢筈岳縦走コース往復」。縦走コース登山口と山頂を往復するどきどきわくわくの約3時間半でした。
本音は、JR指宿枕崎線の入野駅を起点にしたかった



今回は、登山口周辺の駐車場情報を確認したくて、縦走コース登山口近くに車を止め、山頂との往復をしてきましたが、本音を言えば、JR指宿枕崎線の入野駅まで列車を使い、アプローチしたかったです。鹿児島中央駅を早朝6時20分発の列車で山川駅まで乗車し、一足先に指宿駅を出て山川駅で接続待機している枕崎行きの列車に乗り換えれば、8時1分には入野駅に着くからです。山川駅で接続時間が3分間しかないという何というスリリングで、しかも素晴らしい列車のリレーだろう、と感動したからです。
山歩きの鉄則は、早い時間にスタートして、明るいうちに下山することは、今更言うまでもありませんよね。ちなみに、山の達人Iさんは、鹿児島中央駅4時46分発の山川行きで向かうそうです。山川駅6時2分着、山川駅6時11分発の枕崎行きに乗り換えて、入野駅6時36分着。上には上がいるものだと感心しました。
開聞岳と開聞岩の見事なコラボレーション

薩摩富士こと開聞岳(標高924m)を眼前に望む矢筈岳の標高は359m。
山頂近くの標高333m地点には「開聞岩」と呼ばれる岩があります。背後に見える開聞岳とそっくり。海苔でも巻いてパクッと食べたくなるような三角おにぎり形の岩です。山と岩、この2つのシルエットの見事なコラボレーションを写真に収めた瞬間、疲れも一気に飛んでいきました。
久々の山歩きで、膝が笑った×2。準備運動はしっかりと!

さてさて、頂上に至るまでには、山あり谷あり、それは難儀なことでした。
7年近く山歩きしていないうちに、体重は加速度的に増え、しかも低山とはいえ初めて登る山。駐車場の下見だけにしようかという甘い考えで縦走コース登山口に着いたのが11時近く。しかし、登山口を見たからには「登らで帰りょうか」と僕の小さな魂が叫ぶのです。

そうだ、山歩きの本やスマホアプリでイメージトレーニングしてきたのだから…と、とにかく歩いてみよう。そう言い聞かせながらも、このままだと昼前に頂上に着くのは無理だと焦りがありました。10分も歩かないうちに脚が突っ張っているのを実感。倒木をまたぐのも一苦労。そうして初めて、屈伸運動も、足首クリクリもせずに歩き始めたことに気が付きました。少し平らな場所で準備運動し、再出発した次第。
コースのハイライト「西郷ドン岩」にもたれかかって一休み



矢筈岳縦走コースのハイライトが「西郷ドン岩」。なぜそう呼ばれるのかは、海岸沿いから見上げると分かるといいます。3枚の写真は、登山道脇の西郷ドン岩・岩場からの眺め・瀬平公園東側駐車場から見上げた西郷ドン岩(電柱の上の方にある岩)です。
西郷隆盛銅像のような形に見える岩の横に、愛犬ツンのように見える岩が並んでいるというのが命名の由来です。
西郷ドン岩は、縦走コース登山口から登り始めて約30分です。たったこれだけの距離でも、もう汗だくに。岩にもたれかかりながら、水分とチョコレートを補給して一休み。西郷ドン岩に背中を押されるように歩き出し、斜面を慎重に渡り切り、えーっと次は…と、ピンクのリボンテープや赤いテープを目印にコース難関の岩場へ。
最初の岩場はロープを伝って難なくクリア

平日の昼間なので、誰ともすれ違うことなく、少し孤独感も出てきた頃に、最初に現れた岩場。ここは、ロープを伝って難なくクリアしました。コースが整備されていることに改めて感謝。山を愛する人たちに見守られているようで、温かい気持ちになりました。
コースの難所は安全優先で「巻道」を選択



「刀剣岩」を過ぎると、ルート選択の標識が現れました。「岩ルート」それとも「巻道」? 聞かれるまでもなく、安全優先で巻道を選択しました。巻道でも、岩を巻くようにロープが張られています。しかも、横たわる大きな倒木も乗り越えるには、ロープを持つ手を途中で変えながら、念仏のように「三点確保」と唱えながら進みました。ここを過ぎると、後は細尾根を行くのみ。冒頭で触れた「開聞岩」を過ぎると山頂です。頂上で開聞岳におにぎりをお供えして下山の無事をお願いしました。



【おまけ】物袋(もって)農村公園周辺の駐車スペース情報



今回、矢筈岳登山の近くで駐車スペースとして紹介するのは、物袋(もって)農村公園の前にある空きスペースと海沿いの空きスペースです。なるべく乗り合わせて行くのがお勧めです。少し距離はありますが、西郷ドン岩を見上げるところで紹介した「瀬平公園東側駐車場」もあります。